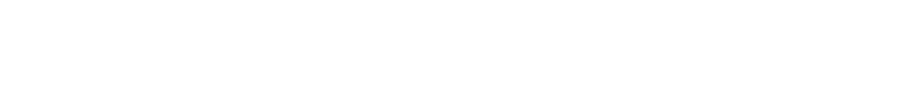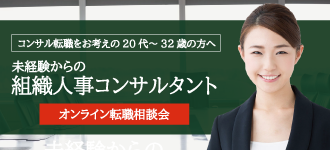組織人事コンサルタントへの転職を支援!転職エージェントのムービン職業紹介(許可番号:13-ユ-040418)

組織人事コンサルタント転職 トップ > 人事転職コラム > 人事労務 > 給与計算業務 -人事の仕事(人事労務)-
給与計算業務
-人事の仕事(人事労務)-
給与計算業務は、従業員の生活に直結する極めて重要な業務です。昇給・降格に伴う月例給与の変動、育児や介護などライフステージの変化に応じた短時間勤務制度適用時の給与計算、各種手当(住宅手当、通勤手当など)の正確な処理は、従業員からの信頼を維持し、組織全体のエンゲージメントを高める上で不可欠と言えるでしょう。
会社が従業員に給与や賞与を支払う際、所得税や住民税、社会保険料などを適切に計算し、控除(天引き)した上で支払います。特に所得税については、会社が従業員に代わって国に納付する「源泉徴収制度」が採用されています。この源泉徴収の仕組みを正しく理解し、運用することが給与計算業務の核となります。
源泉徴収の対象となる主なものには、毎月の給与、賞与、そして退職金などがあります。
■ 所得税の源泉徴収:毎月の給与
毎月の給与から源泉徴収する所得税額は、以下の手順で計算します。
課税対象額の算出:
総支給額から、法律で定められた非課税の手当(例:一定限度額内の通勤手当)と、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)、雇用保険料を控除します。
課税対象額 = 総支給額 - 非課税通勤手当 - 社会保険料等
源泉徴収税額の特定:
上記1で算出した課税対象額と、従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいた扶養親族等の数を、国税庁が毎年発行する「源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて、その月の源泉徴収税額を決定します。
■ 賞与にかかる源泉徴収
賞与から源泉徴収する所得税額は、以下の手順で計算します。
基準額の算出:
賞与支給月の前月の社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象額)を求めます。
税率の特定:
上記1で算出した金額と扶養親族等の数を、国税庁が発行する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて、賞与にかかる所得税の税率を求めます。
源泉徴収税額の計算:
支給する賞与の金額(社会保険料控除後)に、上記2で求めた税率を乗じて源泉徴収税額を算出します。
賞与の源泉徴収税額 = (賞与の額 - 社会保険料等) × 賞与の所得税率
※前月の給与がない場合や、賞与額が前月給与の10倍を超える場合など、特殊なケースでは計算方法が異なるため注意が必要です。
■ 退職金にかかる源泉徴収
退職金にかかる所得税は、他の所得と分離して計算されます(分離課税)。計算方法は、従業員が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで大きく異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合:
退職所得の金額に応じた所得税率及び復興特別所得税率を乗じて税額を算出します。退職所得は、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた後、原則としてさらに1/2にした金額となります(役員等で勤続年数5年以下の場合は1/2にしないなど例外あり)。
1.退職所得控除額の計算:
勤続20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
勤続20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
2.課税退職所得金額の計算:
課税退職所得金額 = (収入金額(源泉徴収される前の退職手当等の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 (ただし、役員等で勤続年数が5年以下の場合は、1/2を乗じません)
3.源泉徴収税額の計算:
上記2で算出した課税退職所得金額に応じた所得税額を「退職所得の源泉徴収税額の速算表」(国税庁)などを用いて計算し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算します。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合:
退職金の支払金額に対し、一律 20.42% (所得税20% + 復興特別所得税0.42%)の税率を乗じて源泉徴収税額を算出します。この場合、従業員自身で確定申告を行い、正しい税額に精算する必要があります。
時間が限られている方にもおすすめ!
たった5分で、組織人事コンサルタントとしてのキャリア像を把握でき、自分に向いているかどうかを判断するための材料を得ることができます。
キャリアアップを目指す場合や、現職でのやりがいや報酬に不満がある場合など、転職を決意する背後にあるさまざまな要因をご紹介。
これらの要因を理解し、自分の転職活動にどう活かすかを考えることで、成功の確率を高めましょう。
どのファームがどのような業界に強みを持っているのか、またそのファームの企業文化や働き方の特徴を把握することで、自分のキャリアに最適な転職先を選ぶ際の参考にすることができます。
お一人お一人に合わせた転職支援、専任のコンサルタントがサポート
ムービンでは大手には出来ない、お一人お一人に合わせた転職支援をご提供しております。
組織人事コンサルタントへのご転職をお考えの方は、ご自身では気づかれない可能性を見つけるためにもぜひ一度ご相談ください。